「建物の解体を進めたら、地中から杭が出てきた…」
「土地の売却を考えているけど、杭は抜かないといけないの?」
建物の解体や土地の再利用を計画する中で、「杭抜き工事」という言葉を初めて耳にし、費用や工法について不安を感じていませんか?
杭抜き工事は、普段あまり馴染みのない専門的な工事ですが、土地の価値を維持し、将来のトラブルを防ぐために非常に重要です。
この記事では、杭抜き工事に関する専門知識を持つプロの視点から、以下の内容を分かりやすく解説します。
- 杭抜き工事の必要性
- 杭抜き工事にかかる費用相場と単価
- 現場の状況で費用が変わる6つの要因
- 代表的な杭抜き工法(ケーシング工法など)の特徴と比較
この記事を最後まで読めば、杭抜き工事の全体像を理解し、安心して工事を依頼するための知識が身につきます。

在住ビジネスでは杭引抜き工事を全国対応。
経験豊富な地盤専門スタッフがお手伝いさせていただきます。
※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
目次
杭抜き工事とは?その必要性を解説
そもそも、なぜ杭抜き工事が必要なのでしょうか。その役割と、工事を行わなかった場合のリスクについて解説します。
杭抜き工事の役割
「杭」とは、軟弱な地盤に建物を建てる際に、建物の沈下を防いで安全性を高めるために地中に打つものです。
建物を解体する際は地上の構造物だけでなく、地中に埋まっているこの杭も撤去し、土地を更地の状態に戻します。この地中の杭を撤去する作業が「杭抜き工事」です。
杭を抜かない場合のリスクと問題点
建物が建てられた際の図面や資料が無く、地中に杭が埋まっているかどうか分からない場合もあります。実際には「更地にして次の建物を建てようとしたときに、想定していなかった杭が見つかった」といった話も聞かれます。杭を抜かなかった場合は以下のようなリスクがありますので、注意しましょう。
- 新しい建物の障害になることがある
土地に新しい建物を建てる際、古い杭が残っていると、新しい基礎の設計・施工の邪魔になることがあります。新規の建物の計画によりますが、杭を抜く必要が発生した場合、余計なコストが発生します。 - 土地の資産価値が下がる
杭が残っている土地は「地中障害物あり」と見なされ、不動産としての資産価値が大幅に低下します。売却時に買い手が見つかりにくくなったり、売却価格が安くなったりする原因となります。 - 地盤沈下の原因になる
古いコンクリート杭は、時間とともに劣化・風化する可能性があります。杭が腐食して地中に空洞ができると、地盤沈下を引き起こすリスクがあります。
解体後に新しい建物を建てる場合、基本的には建物の形状や解体後の地盤調査の結果によって新しく杭を設計し、地盤補強工事を行う必要があります。つまり、「地中に残っている杭をそのまま利用する」ということはできない場合が多くあるのです。
杭抜き工事の費用相場と単価
杭抜き工事の費用は、現場の状況によって大きく変動しますが、まずは目安となる相場を把握することが重要です。
費用相場は1mあたり1.5万円から5万円
杭抜き工事の費用は、杭1mあたりの単価で計算されるのが一般的です。
費用相場は、1mあたりおおよそ15,000円~50,000円が目安となります。例えば、長さ10mの杭を1本抜く場合、15万円~50万円程度の費用がかかる計算です。
ただし、これはあくまで目安の金額です。実際の費用は、次に解説する様々な要因によって変動します。正確な金額を知るためには、必ず専門業者に現地調査を依頼し、見積もりを取得しましょう。
費用を左右する6つの変動要因
杭抜き工事の費用は、画一的なものではなく、以下の6つの要因によって大きく左右されます。見積もりを見る際は、これらの要素がどのように反映されているかを確認することが大切です。
杭の種類
杭にはコンクリート製のものと鋼管(鉄製)のものなど、様々な杭があります。杭の種類によって撤去の難易度や処分費用が異なるため、工事費用に影響します。一般的に、コンクリート杭の方が重量があり、処分費用も高くなる傾向があります。
杭の直径・長さ・本数
杭の直径が太く、長ければ長いほど、そして本数が多ければ多いほど、工事の規模が大きくなり費用は高くなります。これは、作業時間や使用する重機の大きさ、処分する杭の量が増えるためです。見積もりでは、杭の規模が正確に記載されているか確認しましょう。
採用する杭抜き工法
杭を抜くための工法は複数あり、どの工法を採用するかで費用が変わります。例えば、周辺環境への配慮が必要な現場では、低騒音・低振動の工法が選ばれますが、その分コストが高くなることがあります。工法の選定は、現場の状況と予算のバランスを考えて決定されます。
現場の立地条件と搬入経路
工事現場の周辺道路が狭く、大型重機の搬入が難しい場合は、小型の重機を使用したり、特別な搬入方法が必要になったりするため、費用が割高になることがあります。また、電線や隣接する建物との距離なども、作業の難易度を上げ、費用に影響を与える要因です。
地盤の状況と埋め戻し方法
地盤が非常に硬い、あるいは逆に軟弱である場合、杭抜き作業の難易度が上がります。また、杭を抜いた後にできる穴を埋め戻す作業も必要です。「埋め戻し」とは、杭を抜いた後の空洞を砂やセメントミルクなどで充填し、地盤を安定させる作業のことです。この埋め戻しに用いる材料によっても費用は変動します。
杭の処分費用
引き抜いた杭は、産業廃棄物として法律に基づき適正に処分する必要があり、その処分費用も工事費に含まれます。杭の材質(コンクリート、鉄など)や総重量によって処分費用は異なります。
【比較】杭抜き工事の代表的な工法
杭抜き工事には、現場の状況や杭の種類に応じて様々な工法が存在します。ここでは、代表的な3つの工法の特徴を解説します。
ケーシング工法(オールケーシング工法)
「ケーシング工法」とは、孔壁(穴の壁)を保護するための鋼管(ケーシングチューブ)を地面に圧入し、その中で杭を引き抜く工法です。
- メリット:
ケーシングで孔壁を保護するため、周辺地盤の崩壊を防ぎ、近隣への影響(騒音・振動)を最小限に抑えられるのが最大の特長です。安全性と信頼性が非常に高く、市街地の工事で最も一般的に採用されています。 - デメリット:
大型の重機が必要となり、工程も複雑になるため、他の工法に比べて費用が高くなる傾向があります。
チャッキング工法(杭打機引抜工法)
「チャッキング工法」とは、既存杭にケーシングをかぶせて地盤と既存杭の縁切りをした後に、杭先端をチャッキング(杭をケーシングに内包)してそのまま引き上げる工法です。
- メリット:
引き抜き中に杭が折れるリスクが軽減されます(※斜杭の場合を除く)。また杭底部からの埋め戻しが選択できる為、確実な埋め戻しが可能です。 - デメリット:
他の工法と比較して、工期が長く、費用も高くなる傾向があります。
輪投げ工法
「輪投げ工法」とは、杭の頭が地中に埋まっていて掴めない場合に用いられる特殊な工法です。杭の周りを掘削し、ワイヤーを輪のようにして杭に引っ掛け、クレーンで引き上げます。
- メリット:
他の工法では対応できないような、杭頭が地中深くにある場合に有効です。 - デメリット:
杭の周りを掘削する手間がかかり、適用できる状況が限られます。また、杭が地中に残ってしまうリスクもあります。
杭頭処理(杭頭出し)
杭頭処理(くいとうしょり)とは、杭を完全に引き抜くのではなく、地中の一定の深さまで掘り下げ、杭の上部(頭)だけを解体・撤去する方法です。
- メリット
杭の完全な撤去が不要な場合に採用されることがあります。 - デメリット
地中に杭が残ることになるため、土地の売却などを考えている場合は、将来的なリスクについて慎重に検討する必要があります。
工法別の費用・騒音・工期の比較表
各工法の特徴を一覧で比較してみましょう。
| 項目 | ケーシング工法 | チャッキング工法 | 輪投げ工法 | 杭頭処理 |
|---|---|---|---|---|
| 費用 | 高い | 高い | 状況による | やや安い |
| 騒音・振動 | 小さい | やや大きい | やや大きい | 小さい |
| 工期 | 長め | 長め | 状況による | 短め |
| 周辺地盤への影響 | 少ない | やや大きい | やや大きい | 小さい |
| 主な適用条件 | 市街地、軟弱地盤、安全性を最優先する場合 | 杭頭が露出している、周辺への影響が少ない現場 | 杭頭が地中に埋まっている場合 | 杭の完全な撤去が不要な場合 |
比較表で見るとこのようになりますが、現場状況や杭の種類によって施工可能か否か、また予算内に収まるか否かという課題もありますので、施工の実施判断、施工方法においては、専門業者と綿密な摺合せが必要になると思います。また、それぞれの工法にもさらに細かく種類あり、それぞれに特徴が異なる場合もございますのでご留意ください。
杭抜き工事に関するよくある質問
最後に、杭抜き工事に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。
Q. 杭は必ず抜く必要がありますか?
A. 将来的に土地の売却や新たな建築を少しでも考えている場合は、抜くのが理想。ですが・・
杭が残っていると、土地の資産価値が下がり、将来の工事の妨げになる場合もありますので、解体時に抜いておくのが理想ではありますが、杭の引抜き工事は多くの場合、高額の費用が発生します。個人の場合は費用負担ができないケースもありますので、現実的には見積り金額を見てからの最終判断という事になります。
Q. 近隣への騒音や振動の影響は?
A. 工法によって異なりますが、影響を最小限に抑えることは可能です。
ケーシング工法のように、低騒音・低振動の工法があります。事前に業者とよく相談し、対策を講じてもらいましょう。
また対策の一つとして「近隣建物調査」を行うことも挙げられます。工事を行う前に近隣状況を調査することで、後々の近隣トラブルなどへの対策につながります。在住ビジネスでは近隣建物調査も承っておりますので、ご相談ください。
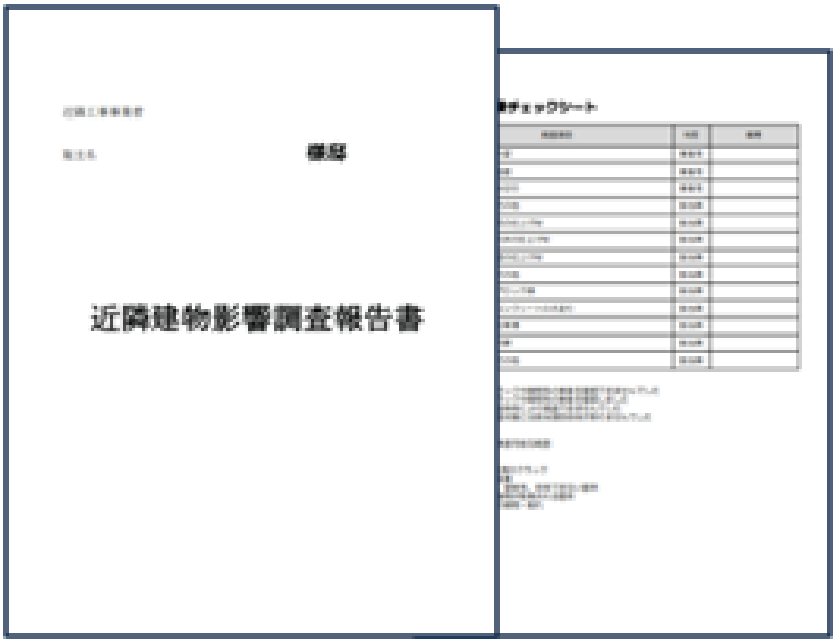

Q. 工事期間はどのくらいかかりますか?
A. 杭の本数や長さ、現場の状況によりますが、数日~数週間かかるのが一般的です。
例えば、10本程度の杭であれば1週間前後で完了することが多いですが、大規模な現場では1ヶ月以上かかることもあります。正確な工期は、業者に見積もりを依頼する際に確認してください。
Q. 杭を残したまま土地を売却できますか?
A. 可能ですが、多くのデメリットがあるため推奨されません。
杭が残っていることは「地中障害物」という瑕疵(欠陥)にあたります。そのため、売却価格を低く設定するなどの必要が出てくる可能性があります。引抜く予算がある場合は、撤去することをお勧めしますが、難しい場合は、既存杭の有無を正確に把握して売却時の重要事項説明等で記載するなり、購入者にキチンと説明することを心がけましょう。
まとめ
この記事では、杭抜き工事の費用相場から代表的な工法、信頼できる業者の選び方までを網羅的に解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- 費用の目安
1mあたり1.5万円~5万円が相場だが、杭の種類や本数、現場の状況で大きく変動する。 - 代表的な工法
安全性・信頼性の高い「ケーシング工法」が主流だが、現場に応じて最適な工法が選ばれる。 - 工事の必要性
将来の土地利用や資産価値の維持、トラブル防止のために、杭抜き工事は原則として必要。
杭抜き工事は、見えない地中の問題を解決し、大切な資産である土地を未来に活かすための重要なステップです。
「杭の引抜きをお願いしたいが、誰に相談したらよいか分からない…」
「まずは何からすればよいのか分からない…」
在住ビジネスは、そういったご相談も丁寧に対応いたします。全国70社以上の地盤会社と協力体制を組むことにより、全国対応できる万全な体制です。お困りごとがございましたら、是非お問い合わせください。
※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
