「この物件は新耐震基準です」「ご自宅は旧耐震ですね」
中古住宅の購入を検討したり、ご自宅の耐震性について調べたりする中で、「新耐震(しんたいしん)」「旧耐震(きゅうたいしん)」という言葉を耳にしたことはありませんか?
地震大国である日本に住む私たちにとって、住まいの耐震性は命と財産を守る上で非常に重要な要素です。しかし、この2つの基準の違いや、ご自身の家がどちらに該当するのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。
この記事では、建築や不動産の専門知識がない方にも分かりやすく、以下の点を詳しく解説します。
- 新耐震基準と旧耐震基準の根本的な違い
- 基準が切り替わった「いつから」という明確な日付
- ご自宅や検討中の物件がどちらかを見分ける具体的な方法
- それぞれのメリット・デメリットや資産価値への影響
- 旧耐震住宅の場合に取るべき対策
この記事を読めば、新耐震と旧耐震に関する疑問が解消され、安心して住宅選びや今後の対策を進められるでしょう。
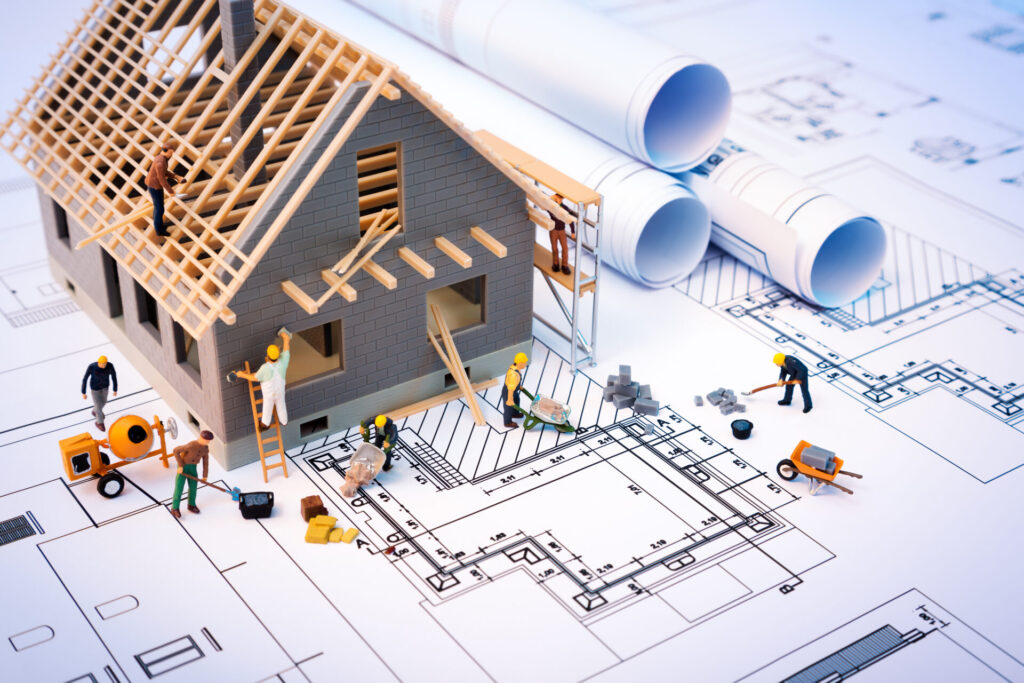
在住ビジネスでは、パソコン上で振動台実験を再現できる「wallstat」の入力代行を承っております。
また万が一の建物倒壊に備え、地震保険とも併用可能な「地震建替え保証」を取り扱っております。
詳しくはこちらのボタンからご確認ください。
新耐震基準と旧耐震基準の違い
まずは、新耐震基準と旧耐震基準の最も基本的な違いについて見ていきましょう。この2つの基準は、単に古いか新しいかだけでなく、想定している地震の規模や、建物に求められる性能が根本的に異なります。
比較表で見る新耐震と旧耐震の概要
一目で違いがわかるように、それぞれの基準のポイントを比較表にまとめました。
| 項目 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 |
|---|---|---|
| 基準の時期 | 1981年5月31日までの建築確認 | 1981年6月1日以降の建築確認 |
| 耐震性能の目安 | 震度5強程度の地震で倒壊しない | 震度6強~7の地震で倒壊しない |
| 想定する地震 | 中規模の地震(数十年に一度) | 大規模な地震(数百年に一度) |
| 設計思想 | 建物が全壊・半壊しないこと | 人命の安全確保を最優先 |
| メリット | 物件価格が比較的安い | 安全性が高く、資産価値が維持されやすい |
| デメリット | 耐震性が低く、税制優遇が受けにくい | 物件価格が比較的高め |
基準はいつから?1981年6月1日が境目
新耐震基準と旧耐震基準を分ける運命の日は、1981年(昭和56年)6月1日です。
この日、建築基準法が大きく改正され、より厳しい耐震性能が求められるようになりました。重要なのは、この日付が「建物の完成日(竣工日)」ではなく、「建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう)が交付された日」を指すという点です。
- 旧耐震基準
1981年5月31日までに建築確認を受けた建物 - 新耐震基準
1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物
建築確認とは、建物の建築計画が法律や条例に適合しているかを行政が審査する手続きのことです。この審査をクリアして初めて工事に着手できるため、実際の完成は建築確認日から数ヶ月〜1年以上後になることもあります。
基準改正の背景となった宮城沖地震
なぜ1981年に基準が大きく見直されたのでしょうか。そのきっかけとなったのが、1978年(昭和53年)に発生した宮城県沖地震です。
この地震では、最大震度5を観測し、ブロック塀の倒壊や建物の損壊によって多くの死傷者が出ました。特に、新しかったはずの鉄筋コンクリート造の建物にも被害が及んだことから、従来の耐震基準では不十分であることが明らかになりました。
この甚大な被害を教訓に、より大規模な地震にも耐えうる住宅を目指して、建築基準法の大規模な改正、すなわち新耐震基準の導入へと繋がったのです。
耐震性能の具体的な違い
新耐震と旧耐震の最も大きな違いは、想定する地震の揺れに対する「耐震性能」です。具体的にどの程度の地震に耐えられる設計になっているのかを見ていきましょう。
旧耐震基準「震度5強で倒壊しない」
旧耐震基準は、数十年に一度発生するような中規模の地震を想定しています。
具体的には、「震度5強程度の揺れを受けても、建物が即座に倒壊・崩壊しないこと」を目標としています。あくまで建物の損傷を防ぐことが主眼であり、震度6以上の大規模な地震は想定されていませんでした。そのため、大きな地震が発生した際には、建物が倒壊し、人命に関わる危険性があると考えられています。
新耐震基準「震度6強から7でも倒壊しない」
一方、新耐震基準は、宮城沖地震の教訓から、より大規模な地震を想定して策定されました。
中規模の地震(震度5強程度)に対しては「ほとんど損傷しない」レベルが求められます。さらに、「震度6強から7に達する大規模な地震でも、建物の倒壊・崩壊を免れ、中にいる人の命を守ること」が最大の目標とされています。
つまり、建物に一定の損傷は受けるかもしれないが、人命の安全確保を最優先する、という設計思想に大きく転換したのが新耐震基準です。
2000年基準とは
新耐震基準をさらに強化するものとして「2000年基準」も存在します。これは、1995年の阪神・淡路大震災の被害を受けて、2000年6月1日に施行された基準で、特に木造住宅に関する規定がより厳格化されました。
主な改正点は以下の通りです。
- 地盤調査の事実上の義務化
建物を建てる前に地盤の強度を調査し、その結果に応じた基礎設計が求められるようになりました。 - 耐力壁の配置バランスの規定
地震の揺れに耐える「耐力壁」を、建物の四隅にバランス良く配置することが義務付けられました。 - 柱や筋交いの接合部に金物を使用
地震の際に柱が土台から抜けたり、筋交いが外れたりするのを防ぐため、指定された金物で補強することが明確に規定されました。
2025年の建築基準法改正
さらに2025年4月に、建築基準法が改正されました。現在、新築で家を建てる場合は、この2025年に改正された建築基準法に適合させる必要があります。
こちらの内容については以下のコラムにまとめておりますので、ご興味のある方は是非ご一読ください。
https://zaijubiz.jp/column/2024-08-09/
それでも耐震性能に不安を感じたら?
近年、想像以上の地震も起きている日本。基準に適合していても「これから建てる自宅が倒壊したらどうしよう」と不安を抱く方もいらっしゃるかと思います。
そこでおすすめしたいのが、在住ビジネスの「wallstat+地震建替え保証」です。
wallstatとは、【耐震性能の見える化】を実現したソフトであり、振動台実験をパソコン上で再現することができます。以下の動画をご覧ください。動画内の「耐震等級1以下」が旧耐震基準、「耐震等級1」「耐震等級2」「耐震等級3」が新耐震基準のそれぞれの等級を表しています。このようにwallstatで耐震性能を見える化することで、安心材料にもなるのではないでしょうか。
さらに在住ビジネスの地震建替え保証は、万が一半壊以上の損害を受けてしまった場合に建物金額の100%を保証いたします。
wallstatと地震建替え保証を掛けあわせることで、「倒壊しても保証がある安心」から「倒壊させない確かな安心」を目指しています。詳細は以下のボタンからご確認ください。
※こちらは新築向けのサービスです。
※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。ご入居者の方は、住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
新耐震か旧耐震かの見分け方
ご自宅や購入を検討している中古住宅が、新耐震基準か旧耐震基準かを見分けるには、どうすればよいのでしょうか。最も確実な方法から、簡易的な判断方法までを解説します。
建築確認済証の日付で確認する
最も確実で正確な方法は、「建築確認済証」に記載されている日付を確認することです。
建築確認済証とは、その建物の建築計画が法的に認められたことを証明する書類で、通常は建物の設計図書などと一緒に保管されています。この書類に記載されている「確認済証交付年月日」が1981年(昭和56年)6月1日以降であれば、その建物は新耐震基準で建てられています。
中古住宅の購入を検討している場合は、不動産会社に依頼すれば確認してもらえます。ご自宅の書類が見当たらない場合は、管轄の役所(市役所や区役所の建築指導課など)で「建築計画概要書」を閲覧することで確認できる場合があります。
築年数で判断する際の注意点
多くの方が参考にするのが「築年数」ですが、これには注意が必要です。
一般的に、建築確認から建物の完成(竣工)までには数ヶ月から1年程度のタイムラグがあります。そのため、築年数だけで判断するのは不確実です。
- 1983年(昭和58年)以降に建てられた建物
新耐震基準である可能性が非常に高いです。 - 1981年6月1日〜1982年末頃に建てられた建物
旧耐震基準で建築確認を受け、新耐震基準の施行後に完成した可能性があります。この期間の物件は特に注意が必要です。
あくまで目安として考え、最終的には建築確認済証で確認することをおすすめします。
登記簿謄本(登記事項証明書)で確認する
法務局で取得できる「登記簿謄本(登記事項証明書)」でも、建物の情報を確認できます。
表題部にある「原因及びその日付」の欄に「昭和〇年〇月〇日新築」といった記載があります。しかし、この日付は建物が完成した日(竣工日)を示すため、築年数で判断するのと同じ注意点があります。1981年築や1982年築の場合は、この日付だけでは新耐震か旧耐震かを断定できません。
新耐震・旧耐震住宅のメリットとデメリット
耐震性の違いは、安全性だけでなく、資産価値や税金の面にも影響します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身のライフプランに合った選択をしましょう。
新耐震基準住宅のメリット・デメリット
メリット
- 安全性が高い
震度6強〜7の大規模地震でも倒壊しにくい設計のため、安心して暮らせます。 - 資産価値が維持されやすい
耐震性の高さが評価され、売却時にも価格が下がりにくく、買い手も見つかりやすい傾向にあります。 - 各種優遇措置を受けやすい
住宅ローン控除や地震保険料の割引など、税制上のメリットを受けられます。
デメリット
- 耐震性能が高いほど物件価格が高い
旧耐震基準の物件に比べて、建築コストや安全性の価値が反映されるため、販売価格は高くなる傾向があります。
旧耐震基準住宅のメリット・デメリット
メリット
- 物件価格が安い
同程度の広さや立地であれば、新耐震基準の物件よりも安く購入できる可能性があります。 - 好立地の物件が見つかることも
都心部や駅近など、利便性の高い場所に建てられているケースも少なくありません。
デメリット
- 耐震性に不安がある
大規模な地震に対する安全性が確保されておらず、倒壊のリスクがあります。 - 資産価値が低い
耐震性の低さから評価が低く、将来的に売却しにくい、または価格が大きく下がる可能性があります。 - 税制優遇が受けにくい
住宅ローン控除や不動産取得税の軽減措置など、多くの優遇制度の対象外となる場合があります。 - リフォーム費用がかかる
安心して住むためには、耐震補強工事が必要になるケースが多く、追加で数百万円の費用がかかる可能性があります。
資産価値・住宅ローン・税制優遇の違い
新耐震と旧耐震では、お金の面でも大きな違いが生まれます。
- 住宅ローン控除
原則として新耐震基準に適合していることが適用の条件です。旧耐震でも「耐震基準適合証明書」などを取得すれば利用できる場合がありますが、手続きと費用が必要です。 - 地震保険料
新耐震基準の建物は、建築年に応じて10%〜30%の割引が適用されます。旧耐震の建物は割引がありません。 - 不動産取得税・登録免許税
これらの税金の軽減措置も、多くの場合、新耐震基準を満たしていることが条件となります。 - 資産価値(担保評価)
金融機関が住宅ローンを融資する際、建物の担保価値を評価します。旧耐震の建物は担保評価が低くなるため、希望する額の融資を受けられない可能性があります。
旧耐震基準の住宅で取るべき対策
もしご自宅や購入を検討している物件が旧耐震基準だった場合、どうすればよいのでしょうか。安全性を確保し、安心して暮らすための対策をご紹介します。
まずは専門家による耐震診断を受ける
最初に行うべきことは、専門家による耐震診断です。
耐震診断とは、建物の現状を調査し、地震に対する強度を評価することです。建築士事務所やリフォーム会社、専門の診断業者などに依頼できます。費用は木造住宅の場合、10万円〜40万円程度が相場ですが、自治体によっては診断費用の一部を補助してくれる制度もあります。
この診断によって、ご自宅の弱点や、どの程度の補強が必要かが具体的に分かります。
耐震補強工事の種類と費用相場
診断結果に基づき、必要に応じて耐震補強工事を行います。主な工事内容と費用相場は以下の通りです。
- 壁の補強
筋交いや構造用合板を追加して、壁の強度を高めます。
(費用相場:1箇所あたり数万円〜25万円) - 基礎の補修・補強
ひび割れを補修したり、鉄筋コンクリートで基礎を一体化させたりします。
(費用相場:50万円〜150万円) - 屋根の軽量化
重い瓦屋根を、軽い金属屋根などに葺き替えます。建物の重心が下がり、揺れにくくなります。
(費用相場:80万円〜200万円) - 接合部の金物補強
柱と土台、梁などを専用の金物で固定し、地震の揺れで抜けないようにします。
(費用相場:工事全体で20万円〜50万円)
工事の規模や内容によって費用は大きく変動しますが、一般的な木造住宅の耐震補強工事は、総額で100万円〜数百万円程度かかることが多いです。
活用できる補助金・助成金制度
耐震診断や耐震補強工事には、国や地方自治体からの補助金・助成金制度が用意されている場合があります。
制度の内容や補助額、対象となる条件は自治体によって大きく異なります。工事を検討する際は、まずお住まいの市区町村の役所(建築指導課や防災課など)の窓口に問い合わせてみましょう。お得に工事ができる可能性があるので、必ず確認することをおすすめします。
新耐震・旧耐震に関するよくある質問
最後に、新耐震・旧耐震に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。
1981年築の建物はどちらの基準?
「1981年築」というだけでは、新耐震か旧耐震かを判断することはできません。
重要なのは「建築確認日」です。1981年6月1日以降に建築確認を受けていれば新耐震、それ以前であれば旧耐震となります。1981年に完成した建物は、旧耐震基準で建築確認を受けた可能性が高いため、必ず「建築確認済証」で日付を確認してください。
旧耐震のマンションは危険か?
一概に「危険」とは言えませんが、新耐震のマンションに比べて地震リスクが高いのは事実です。
ただし、マンションの場合は、管理組合が主体となって耐震診断や大規模な耐震補強工事を実施しているケースもあります。旧耐震のマンションを検討する際は、価格だけでなく、管理規約や過去の修繕履歴をしっかりと確認し、耐震対策が取られているかを見極めることが非常に重要です。
新耐震基準なら絶対に安全か?
「絶対に安全」とは言い切れません。
新耐震基準は、あくまで「震度6強〜7の地震で倒壊・崩壊しない」ことを目標としており、人命を守ることを最優先にしています。想定を超える規模の災害が起きた場合や、建物の経年劣化、メンテナンス不足によっては、被害が大きくなる可能性もゼロではありません。新耐震基準であっても、定期的な点検やメンテナンスを怠らないことが大切です。
まとめ
今回は、新耐震基準と旧耐震基準の違いについて、見分け方から性能、資産価値への影響まで詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 新耐震と旧耐震の境目は「1981年6月1日」の建築確認日
- 旧耐震は「震度5強」、新耐震は「震度6強〜7」の地震を想定
- 見分け方は「建築確認済証」の日付で確認するのが最も確実
- 旧耐震住宅は価格が安いが、安全性や資産価値にリスクがある
- 旧耐震の場合は、まず専門家による「耐震診断」を検討することが重要
住まいの耐震性は、あなたとご家族の未来を守るための基盤です。この記事で得た知識をもとに、ご自宅の状況を確認し、中古住宅を選ぶ際の確かな判断基準としてお役立てください。もし旧耐震基準の住宅にお住まい、または購入を検討している場合は、専門家に相談し、適切な対策を講じることを強くおすすめします。
また基準に適合していても、「これから建てる建物が本当に倒壊しないのか」「もし倒壊したらどうしよう」。そんな不安を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方におすすめなのが、在住ビジネスの「wallstat+地震建替え保証」です。
wallstat検証で耐震性能を見える化。さらに万が一に備えて、地震保険とも併用可能な地震建替え保証のサービスを提供しております。詳しくは下のボタンからご確認・お問い合わせください。
※こちらは新築向けのサービスです。
※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。ご入居者の方は、住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
